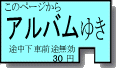<本文は1980年に書いたものです>
表示がおかしい場合はこちらをクリックしてください。
文字を設定する場合はこちらをクリックしてください。
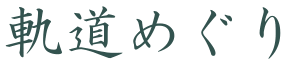
|
第7回 ナロー編その5 太平洋炭鉱

|
|
空車をひいて炭鉱へ帰る
1981年(昭和56年)撮影 |
太平洋炭鉱で働いていた人の話では、鉱員は入社したてでも月収30万にはなるという。持ち家制度が徹底され、社員には土地が安く払い下げられる。炭鉱と言えば古く汚い長屋のような社宅が連想されるが、まるでそのイメージとはかけ離れ、新興住宅地の様相を呈している。さらに3LDKの社宅は無料であるという。しかし、これらはすべて坑内における落盤・爆発事故のリスク、過酷な重労働の代償であろう。実際、自分の家を取得したとたんに転職してしまうケースも見うけられるそうだ。華やかに見える住宅地全体から受ける冷え冷えとした印象もその重荷ゆえか。都会の住宅地とは確かに異なる冷たさだ。釧路はこの日、最低気温マイナス19℃、最高気温も0℃に達しない真冬日であった。そのためなのか・・・・・。
『太平洋炭鉱 部外者の立ち入りを禁ず』と書かれた看板わきの道を入り、ちょうどやってきた総務課の人にねばって坑道の入口に入る許可をもらった。構内に入ると、ガランガランという音が耳に入る。地上10mくらいのところをベルトコンベアが動いている、と、その時は思った。総務課で、今年22才というS氏を紹介され、案内してもらうことになった。歳も近いので、話しやすかった。
「こちらへは仕事ですか?」
「いえ、まだ学生で、旅行です」
「アッ、シャーワセ」
「写真大学の課題か何か?」
「いえ、写真は趣味で」
「アッ、シャーワセ」
万事、この調子であった。
S氏には、まず、休憩所へ案内された。中へ入るとモワッとした湿気と煙が充満していた。学校の教室ほどの広さの休憩所は、そば、うどんの湯気と、煙草の吸いだめによる煙で、ただでさえ暗い休憩所内を一層かすんでみせた。休憩所の隣では鉱員達がヘルメットなどの身支度をし、さらに身体検査(火気のあるものは持ちこめない。だから、鉱員達は煙草の吸いだめをするのだ)を受け、入坑する。
入坑する鉱員達の姿は、出征兵士の後姿に通ずるものがあるのではないか。戦争は知らないが、こう思うのであった。
坑道(斜坑)へ出た100人くらいの鉱員達は、整然と並び、人車を待つ。急勾配なので機関車ではなく、ケーブルにひかれるのだ。 直径5cm はあるだろうか、ケーブルはビュンビュンうなっている。ケーブルは地上に出ると、空中を駆け抜け、巨大なモーターにつながっている。さっき、ベルトコンベアと思ったのでは、このケーブルであったのだ。程なくして、人車が到着し、鉱員達はあっという間に乗りこみ、下ってしまった。まるで奈落の底に落つるがごとく。
「切り端まで往復2時間、休憩1時間、つまり実働は5時間になってしまうんだ」
とS氏は微笑む。でも、その5時間がきついのではと問うと、すっと顔をくもらせ、「そうだ」と答えた。
その後、太平洋炭鉱名物の凸型機関車を見に行った。 軌間は何mmか、架線電圧は何ボルトかと問うと、 「さあ、いかんなあ、勉強不足だ」と笑った。
その間もケーブルは空中をガランガランと走っていたのだろう。撮影や話に熱中して、ケーブルのことなどすっかり忘れていた。ハッ、静寂に気づき戦慄した。ケーブルが止まっている。鉱員達が底に着いたのだろうか。地上は荒涼として人の姿も少ない。しかし、いま踏みしめる大地の地下600m、東西10Km以上に及ぶ坑道の中で、何百人もの人々がうごめいている。それに気がついたとき、戦慄が走ったのであった。地上にいると地下の人々の存在は忘れてしまう。その存在を知らせてくれるのは人間ではなく、機械の動きなのであった。改めて見上げるケーブル、それをたどれば人がいる。ケーブルは不気味であった。
「今、ケーブルが止まったけど、下に着いたんですね」
「いや、上がってきたのかもしれないョ」
あがってきた! そう考えるとほっとする。
S氏と別れ、軌道沿線をぶらぶら歩きながら写真を撮っていたが、ふるえが止まらず、近くの茶店であたたまったが、それでも止まらないので、しかたなくバスでユースに帰った。身も心も冷え切った一日であった。
1980年2月の軌道めぐり
【1980年5月発行キロポスト第88号】