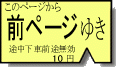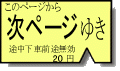表示がおかしい場合はこちらをクリックしてください。
文字を設定する場合はこちらをクリックしてください。
 ドイツ編(前編)
ドイツ編(前編)
ウィーンを朝8時、定刻に発車したモーツアルト号は、12時前にザルツブルグに着く。

| |
|
コンパートメント入口の予約表示。
写真では札の字が飛んでいるが、3列のシートごとの予約区間が書かれている。 上が窓側で、札のない中段は空席を示す。 |
次はドイツ国内のミュンヘンまで停まらないので、ここで入国審査がある、はずであった。イタリアからオーストリアに入るときは夜行で、パスポートも先に『鉄道のポリースマン』に預けていたので、入国審査官と話すことはなかったが、今度はいよいよと待ち構えていた。
ところが、私たちのコンパートメントは素通りで、別にチェックして欲しいわけではないが、ちょっと拍子抜けであった。
ミュンヘンではいわゆるチッキ(鉄道手荷物)でスーツケースを送ることにする。ただでさえ駆け足旅行なのに、これからドイツ国内はすべて一泊ずつとさらにスピードアップするので身軽にしておきたかったのだ。
それらしい窓口へ行き「ケルンへ」と係員の人に頼む。すると、
「ケルン?」と首をかしげ、中の人に大声で「おーい、ケルンなんて駅、知ってるか!?」という感じで尋ねる。
「え、あのケルンなんだけど・・・」と戸惑いながら、ケルンと書いたメモ用紙を渡すと、
「なーんだ、コロンか、おーい、わかったよ、コロンのことだ!」とまた大声で中の人に叫ぶ。
ウィーンではホテル名も伝わらず、今度は有名な都市名も伝えられなかった。ああ、学生時代の第2外国語はなんだったのか。大学時代のドイツ語の講師はとても厳しく、20名以上いたはずのクラスで、最後の試験まで受けたのは数名であった。一応その数名には入っていたのだが、「コラッ、なんという発音をしとる!」という雷が聞こえそうな気がした。
こうしてなんとかスポーツバックだけと身軽になったあとは、あの有名なロマンチック街道の終点、ノイシュヴァンシュタイン城のあるフュッセンへ行く予定なのであるが、ミュンヘンではどうしても寄りたい場所があった。ドイツ博物館である。

| |
|
|
といっても鉄道の展示物を見るためではない。実は第2次世界大戦時の航空機にも興味があって(しかし鉄ちゃんで航空機もとくると、自分でも暗いと思う・・・)ここに展示されているドイツ機をぜひ見たいと思っていたのである。
時間も限られているので入館して一直線に航空機の展示コーナーへ向かう。
「ああ、メッサーシュミットだ、ユンカースだ、ドルニエだ・・・」
特に大戦初期から敗戦まで活躍した日本で言えばゼロ戦に相当するメッサーシュミット109も、実機を見るのは初めてで、なめまわすように見て、触って、撮って、ひとときの興奮を味わった。
その間、本来なめまわして・・・もういい!ってね。
  
|
発車間近の鈍行列車。
(ミュンヘン駅にて) |
ミュンヘンからは鈍行列車。年配の夫婦と同じコンパートメントになり、何か会話したいとは思うものの、ケルンも伝えられない状態では諦めざるを得なかったのは残念。別れ際に、
「ヴィーダーゼーン(さようなら)」と言うと、
「Wiedersehen」と返事が返ってきた。今度は通じた(^^;)
日本へ帰ってから新妻とは「今度はもう少し、言葉を勉強してから行こうね」なんて話をしたのだが、それから丸14年、海外旅行自体が実現していない。
途中でレールバスに乗換え、フュッセンへ。事前に地元の観光協会で斡旋されたノイシュヴァンシュタイン城に近いホテルに泊まる。団体の日本人だらけで、ある意味、日本人の私達がこのホテルを斡旋された理由はわかる。
  
|
ノイシュヴァンシュタイン城(1886年築城)
築城したルートヴィッヒ2世は完成後、わずか3ヶ月で王位を追われたという。 ホーエンシュヴァンガウ城(1836年築城)
ルートヴィッヒ2世は少年時代、この城で過ごした。 ←写真は2枚あります。画面に触れてください。 |
翌日、早速ノイシュヴァンシュタイン城に上る。たまたま一緒になったアメリカ人の家族連れのおばちゃんが、お城の案内人に英語の解説はないのか、と何度も尋ねていたが、返事は「ない」、いや本当は「Nein(ナイン)」(ドイツ語でNoのこと)とぶっきらぼうに首を横に振って愛想がない。困り果てたおばちゃんが、やおらこちらに、
「あなた、ドイツ語わかる?」と尋ねてくる。こちとらドイツ語どころか英語だって怪しいのに、ドイツ語を英語に訳すなんてめっそうもない、慌てて「No、No」と答えると、別の連れが、
「Noじゃなくて、Neinって言わなきゃ」と笑う。
ドイツでは意外に英語が通じない。他でも何度も「Nein」と言われて困ったようだ。
結局、英語の解説テープなら流せるということになり、おばちゃんは小躍りして、
「すばらしいわ、よかったわね」とこちらに抱きつかんばかりに喜んでいる。しかし、繰り返しになるが、残念ながら私たちにはドイツ語であろうと英語であろうと同じことであった。
城内に入ると、アメリカ人家族は、調度品などを見ては「Wonderful!」を連発し、失礼ながら田舎から出てきたおのぼりさんという感じであった。でも、その姿はまるで『大草原の小さな家』からそのまま飛び出してきたようなほのぼのした雰囲気で、見ているこちらも和やかな気分になるのであった。